イタチの侵入を防ぐ外壁の対策方法は?【5mm以上の隙間が危険】外壁の弱点を知り、実践する3つの補強テクニック

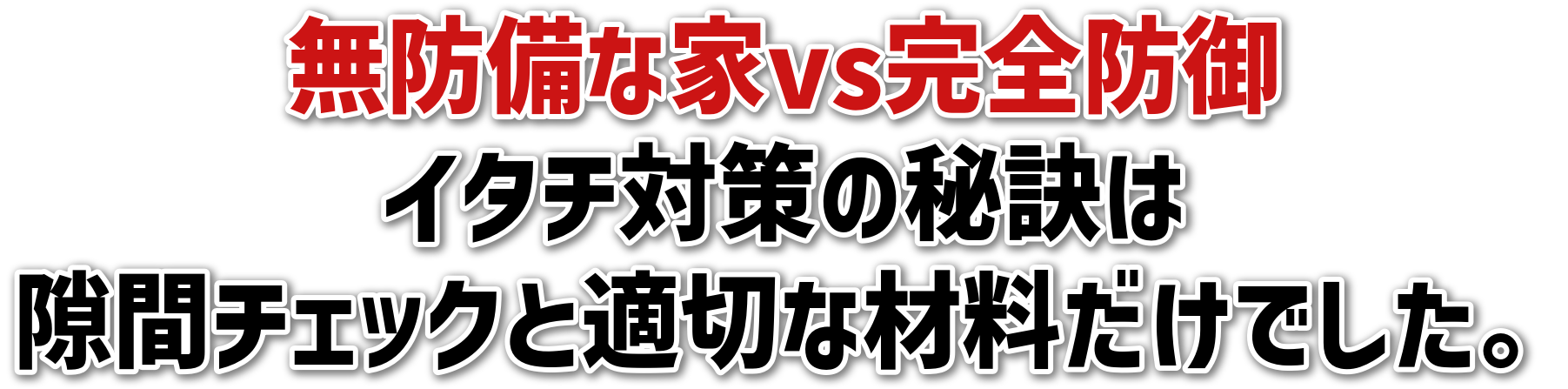
【この記事に書かれてあること】
イタチの侵入で悩んでいませんか?- イタチは5mm以上の隙間から侵入可能
- 軒下や配管周りが主な侵入経路
- 外壁点検は年2回が理想的
- 外壁素材の選択がイタチ対策の鍵
- DIY対策で効果的にイタチを撃退
実は、家の外壁に潜む小さな隙間が大きな問題を引き起こしているかもしれません。
わずか5ミリの隙間がイタチの侵入口になる可能性があるんです。
でも、安心してください。
この記事では、イタチの侵入を防ぐ外壁対策を徹底解説します。
軒下や配管周りの点検方法、効果的な補強材料の選び方、そして驚くほど簡単なDIY対策まで。
年2回の点検で完璧防御を実現しましょう。
さあ、イタチとの戦いに勝つための秘策を一緒に学んでいきましょう!
【もくじ】
イタチの侵入を防ぐ外壁の対策方法とは

イタチが侵入しやすい「5mm以上の隙間」に要注意!
イタチの侵入を防ぐには、5mm以上の隙間をなくすことが重要です。イタチは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。
「え?5mmってどれくらい?」と思った方も多いはず。
イメージしやすいように例えると、500円玉の厚みとほぼ同じです。
こんな小さな隙間でも、イタチにとっては立派な入り口になってしまうんです。
イタチが侵入しやすい場所は主に以下の3つです。
- 外壁と土台の間の隙間
- 配管や電線の貫通部周辺
- 屋根と壁の接合部
「うちは大丈夫だろう」と油断は禁物。
古い家だけでなく、新築の家でも施工ミスで隙間ができていることがあるんです。
隙間を見つけたら、すぐに対策を取ることが大切です。
放っておくと、イタチが「ここが弱点だ!」とばかりに侵入してきてしまいます。
早めの対策で、イタチを寄せ付けない安全な家づくりを心がけましょう。
軒下や配管周りが侵入の危険ゾーン!要チェック箇所
イタチの侵入を防ぐには、軒下と配管周りを重点的にチェックすることが大切です。この2つの場所は、イタチにとって格好の侵入口となっているんです。
まず軒下。
ここはイタチが大好きな場所なんです。
なぜって?
- 雨風をしのげる絶好の隠れ家
- 木の枝や電線からアクセスしやすい
- 家の中に侵入する足がかりになる
軒下の隙間は、イタチにとって絶好の侵入ルートなんです。
次に配管周り。
ここも要注意ポイントです。
配管が壁を貫通している部分は、どうしても隙間ができやすいんです。
イタチはその隙間を見逃しません。
ちょっとした隙間でも、「ここだ!」とばかりに侵入してきます。
チェックする時は、家の外周をぐるっと一周して、じっくり観察しましょう。
特に夕方から夜にかけてがおすすめです。
イタチは夜行性なので、この時間帯に活発に動き回るんです。
「え?夜に外を歩くの?」と思った方も大丈夫。
懐中電灯を使えば、隙間がくっきり見えますよ。
光を当てながら、ゆっくりと壁を見ていけば、小さな隙間も見つけやすくなります。
軒下と配管周りをしっかりチェックして、イタチの侵入を防ぎましょう。
小さな対策が、大きな安心につながるんです。
外壁の点検は年2回が鉄則!春と秋がおすすめ時期
外壁の点検は、年に2回行うのが鉄則です。特におすすめなのは春と秋。
この時期に点検することで、イタチの侵入を効果的に防げます。
なぜ春と秋がいいのでしょうか?
理由は簡単。
- 春:冬の寒さによる外壁の損傷をチェックできる
- 秋:夏の暑さによる外壁の劣化を確認できる
- 両方の季節:イタチの繁殖期と重なるため、侵入リスクが高い
でも、ちょっと待ってください。
この点検、実は家計の味方なんです。
定期的な点検で小さな問題を早めに見つけることで、大きな修理費用を節約できるんです。
「小さな穴を見つけて直すだけで、大工事を避けられた!」なんて嬉しい話もよく聞きます。
点検のコツは、外壁をじっくり観察すること。
特に注意したいのは以下の点です。
- 亀裂やひび割れはないか
- 塗装のはがれや変色はないか
- 木部の腐りはないか
- 雨樋や配管周りの隙間はないか
「でも、高いところは見づらいな...」と思った方も大丈夫。
双眼鏡を使えば、地上から屋根近くまでしっかり見られますよ。
年2回の点検で、イタチから家を守りましょう。
小さな手間が、大きな安心を生み出すんです。
シーリング材や補強材料の選び方と使用方法
イタチの侵入を防ぐには、適切なシーリング材や補強材料を選び、正しく使用することが重要です。正しい材料と方法で、イタチに強い家を作りましょう。
まず、シーリング材の選び方。
イタチ対策に効果的なのは以下の特徴を持つものです。
- 耐久性が高い
- 弾力性がある
- 防水性能が優れている
これらは長持ちし、家の動きにも対応できるんです。
「でも、どうやって使うの?」と思った方も大丈夫。
使い方は簡単です。
- 隙間をよく清掃する
- 必要に応じてプライマーを塗る
- シーリングガンで材料を隙間に充填する
- ヘラで表面を整える
メッシュやパネルタイプの物が効果的です。
特にステンレスメッシュは、イタチの鋭い歯にも負けない強さを持っています。
補強材料の使い方は、隙間や穴をカバーするように取り付けるだけ。
ただし、しっかり固定することが大切です。
イタチは意外と力が強いので、緩い固定だとはがされてしまうかもしれません。
「え?素人でも大丈夫?」と心配な方もいるでしょう。
確かに、難しい場所や大規模な補強は専門家に任せるのが賢明です。
でも、小さな隙間なら自分でも十分対処できます。
シーリング材や補強材料を上手に使って、イタチの侵入を防ぎましょう。
ちょっとした工夫で、家の安全性がグンと上がるんです。
外壁補強は「自分でやる」vs「業者に依頼」どっちがいい?
外壁補強、自分でやるべき?それとも業者に頼むべき?
答えは「状況次第」です。
それぞれのメリット・デメリットを知って、賢く選択しましょう。
まず、自分でやる場合のメリットとデメリットを見てみましょう。
- メリット:費用が安い、すぐに対応できる、達成感がある
- デメリット:技術や道具が必要、危険を伴う、時間がかかる
高所作業や大規模な補強は危険が伴います。
自分の技術と体力を正直に評価しましょう。
次に、業者に依頼する場合のメリットとデメリットです。
- メリット:プロの技術で確実、高所作業も安全、保証がつく
- デメリット:費用が高い、日程調整が必要、業者選びに時間がかかる
確かに業者依頼は高額になりがちです。
でも、長期的に見れば費用対効果は高いんです。
プロの仕事は耐久性が高く、再補強の頻度が減るからです。
では、どう判断すればいいのでしょうか?
以下の点を考えてみましょう。
- 補強の規模:小さな隙間なら自分で、大規模なら業者に
- 技術の難易度:簡単な作業なら自分で、複雑なら業者に
- 時間の余裕:休日にできるなら自分で、忙しければ業者に
- 予算:余裕があれば業者に、tight(きつい)なら自分で
その経験を通じて、自分の限界と業者の必要性がわかってくるはずです。
自分でやるか業者に頼むか、正解は人それぞれです。
大切なのは、安全で確実な補強を行うこと。
それがイタチの侵入を防ぐ最善の方法なんです。
外壁素材の特徴とイタチ対策の効果を比較

木造vs鉄筋コンクリート!イタチに強い建材はどっち?
イタチ対策で考えると、鉄筋コンクリートの方が木造よりも強いんです。「えっ、そうなの?」と思った方も多いはず。
でも、理由を聞けばすぐに納得できますよ。
まず、木造住宅の特徴を見てみましょう。
- 温かみがある
- 建てやすい
- コストが比較的安い
木材は年月とともに収縮したり、膨張したりします。
そのため、小さな隙間ができやすいんです。
イタチにとっては、この隙間が絶好の侵入口になっちゃうんです。
一方、鉄筋コンクリートはどうでしょうか。
- 頑丈で耐久性が高い
- 火災に強い
- 隙間ができにくい
コンクリートは木材と違って、ほとんど収縮や膨張をしません。
そのため、イタチの侵入口になりやすい隙間ができにくいんです。
「でも、コンクリートって冷たそう...」なんて思う方もいるでしょう。
確かに、木造に比べると温かみは少ないかもしれません。
でも、イタチ対策を考えると、その「冷たさ」が逆に味方になるんです。
イタチは暖かい場所を好むので、冷たいコンクリートは彼らにとって魅力的ではないんです。
もちろん、鉄筋コンクリートだからといって100%安全というわけではありません。
配管や換気口など、どうしても必要な開口部からイタチが侵入する可能性はあります。
でも、木造に比べれば、はるかに対策は立てやすいんです。
結論として、イタチ対策という観点では、鉄筋コンクリートの方が木造よりも有利。
家を建てる際や、リフォームを考える際には、このポイントも考慮に入れてみてはいかがでしょうか。
サイディングvs漆喰!イタチ対策に適した外壁材は?
イタチ対策の観点から見ると、漆喰の方がサイディングよりも優れているんです。「えっ、古風な漆喰の方がいいの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、理由を聞けば納得できますよ。
まずは、サイディングの特徴を見てみましょう。
- 様々なデザインが選べる
- 比較的安価
- 施工が簡単
サイディングは板状の材料を重ねて壁を作ります。
そのため、板と板の間に小さな隙間ができやすいんです。
この隙間が、イタチの侵入口になってしまうことがあるんです。
一方、漆喰はどうでしょうか。
- 自然素材で環境にやさしい
- 調湿効果が高い
- 防カビ・防虫効果がある
漆喰は壁全体を覆うように塗るので、イタチが侵入できるような隙間ができにくいんです。
さらに、漆喰には自然な防虫効果があります。
「え、本当に?」と思う方もいるでしょう。
でも、これは科学的に証明されているんです。
漆喰に含まれる成分が、虫やネズミを寄せ付けにくくするんです。
イタチも例外ではありません。
「でも、漆喰って古臭そう...」なんて心配する方もいるかもしれません。
確かに、昔ながらの材料ですが、最近では現代的なデザインに合わせた使い方も増えているんです。
白壁の美しさを活かしたモダンな家も、たくさん建てられています。
もちろん、漆喰だからといって100%安全というわけではありません。
定期的なメンテナンスは必要です。
でも、サイディングに比べれば、はるかにイタチ対策は立てやすいんです。
「漆喰、意外といいかも」そんな風に思えてきませんか?
家の外壁を選ぶとき、イタチ対策という観点からも漆喰を検討してみる価値は十分にありそうです。
新築vs築年数!イタチ侵入リスクが高いのはどっち?
イタチの侵入リスクという観点から見ると、築年数が経った家の方が新築よりもリスクが高いんです。「え、そうなの?」と思った方も多いはず。
でも、理由を聞けばすぐに納得できますよ。
まず、新築の特徴を見てみましょう。
- 建材が新しく、劣化がない
- 設計段階からイタチ対策を考慮できる
- 隙間や亀裂がほとんどない
また、最近の新築では、害獣対策を考慮した設計が増えているんです。
一方、築年数が経った家はどうでしょうか。
- 経年劣化により隙間や亀裂ができやすい
- リフォームの際に新たな隙間ができることも
- 古い建築基準で建てられている可能性がある
時間が経つにつれて、壁や屋根に小さな隙間や亀裂ができやすくなるんです。
これが、イタチの格好の侵入口になってしまうんです。
「うちは築20年以上だけど、大丈夫かな...」なんて心配になってきた方もいるでしょう。
でも、安心してください。
築年数が経っているからといって、必ずしもイタチに侵入されるわけではありません。
大切なのは、定期的な点検とメンテナンスです。
例えば、年に2回、春と秋に家の外回りをチェックする。
小さな隙間を見つけたら、すぐにふさぐ。
そんな小さな心がけが、イタチの侵入を防ぐ大きな力になるんです。
また、リフォームの際には特に注意が必要です。
「せっかくリフォームしたのに、逆にイタチが入りやすくなっちゃった...」なんて悲しいことにならないよう、業者さんとよく相談しながら進めましょう。
新築だからといって油断は禁物。
築年数が経っているからといって諦めることはありません。
どちらの場合も、常に家の状態に気を配り、適切なケアを行うことが、イタチ対策の秘訣なんです。
外壁塗装の種類と効果!シリコン系vsフッ素系
イタチ対策の観点から見ると、フッ素系塗料の方がシリコン系塗料よりも少し優れているんです。「えっ、そうなの?」と思った方も多いでしょう。
でも、理由を聞けばすぐに納得できますよ。
まず、シリコン系塗料の特徴を見てみましょう。
- 耐候性が高い
- 柔軟性があり、ひび割れに強い
- 比較的安価
特に、柔軟性があってひび割れに強いという点は、イタチ対策にも有効です。
小さな亀裂からイタチが侵入するのを防げるんです。
一方、フッ素系塗料はどうでしょうか。
- 超高耐候性
- 汚れがつきにくい
- 耐薬品性が高い
シリコン系塗料よりもさらに長持ちするんです。
これは、イタチ対策にとって大きなメリットなんです。
「でも、フッ素系塗料って高そう...」と心配する方もいるでしょう。
確かに、初期費用はシリコン系よりも高くなります。
でも、長期的に見ると実はお得なんです。
なぜなら、塗り替えの頻度が少なくて済むからです。
さらに、フッ素系塗料は汚れがつきにくいという特徴があります。
これは意外とイタチ対策に効果があるんです。
汚れがつきにくいということは、イタチの爪跡や体の汚れがつきにくいということ。
イタチにとっては、「ここは居心地が悪いな」と感じる要因になるんです。
とはいえ、シリコン系塗料が悪いわけではありません。
予算や家の状況に応じて、適切な選択をすることが大切です。
どちらの塗料を選んでも、定期的なメンテナンスを行うことで、イタチ対策の効果を高められます。
「塗料選びって、こんなに奥が深いんだ」そう感じた方も多いのではないでしょうか。
イタチ対策を考える上で、外壁塗装の選択は思いのほか重要なポイントなんです。
メンテナンス頻度の比較!長期的なコスト削減のコツ
イタチ対策のためのメンテナンス、実は頻度を上げると長期的にはコストが下がるんです。「えっ、頻繁にやる方が安くなるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、理由を聞けばすぐに納得できますよ。
まず、メンテナンスの頻度による違いを見てみましょう。
- 年1回以下:大きな問題が見過ごされやすい
- 年2回(春・秋):多くの専門家が推奨
- 年4回(各季節):最も理想的だが手間がかかる
そうなると、大規模な修理が必要になることも。
ここでグッとお金がかかっちゃうんです。
一方、年2回以上のメンテナンスではどうでしょうか。
- 小さな問題を早期発見できる
- 修理のコストが抑えられる
- イタチの侵入リスクが大幅に減少
これが、長期的なコスト削減につながるんです。
例えば、外壁に5ミリの隙間を見つけたとします。
この段階なら、市販のシーリング材で自分で塞ぐこともできます。
費用は数百円程度。
でも、これを放置すると隙間が広がり、イタチが侵入。
大規模な修理が必要になると、数十万円かかることも。
「うわ、そんなに違うの?」と驚いた方も多いはず。
そうなんです。
小さなメンテナンスを積み重ねることで、大きな出費を防げるんです。
具体的なメンテナンス項目としては、以下のようなものがあります。
- 外壁のひび割れや隙間のチェック
- 屋根や軒下の点検
- 換気口や配管周りの確認
- 庭や周辺環境の整備
同時に、家の寿命も延びるので、一石二鳥なんです。
「定期メンテナンス、やってみようかな」そんな気持ちになってきませんか?
確かに手間はかかりますが、長期的に見ればきっと満足できる結果が得られるはずです。
イタチ対策、やってみようかな」そんな気持ちになってきませんか?
確かに手間はかかりますが、長期的に見ればきっと満足できる結果が得られるはずです。
イタチから家を守りながら、家計も守る。
そんな一石二鳥の効果が、定期的なメンテナンスにはあるんです。
まずは、春と秋の年2回からスタートしてみましょう。
慣れてきたら、季節ごとの年4回に増やすのもいいかもしれません。
大切なのは、続けること。
小さな変化も見逃さない、細やかな目を持つことが、イタチ対策の極意なんです。
「家のメンテナンス、意外と楽しいかも」そんな発見があるかもしれません。
家族で協力して行えば、コミュニケーションの機会にもなりますよ。
イタチ対策を通じて、家族の絆も深まる。
そんな素敵な効果も期待できるんです。
驚くほど簡単!5つの外壁DIY対策でイタチを撃退

ペットボトルの反射光でイタチを寄せ付けない方法
ペットボトルを使った驚くほど簡単なイタチ対策、ご存じですか?実は、このありふれた日用品が強力なイタチ撃退グッズに変身するんです。
まず、透明なペットボトルを用意しましょう。
「えっ、透明じゃないとダメなの?」と思った方、その通りです。
透明だからこそ、光を反射させる効果が抜群なんです。
次に、このペットボトルに水を入れます。
ここでのポイントは、8分目くらいまで水を入れること。
なぜかって?
これくらいの水量が、光の反射と屈折を最大限に引き出すんです。
さて、準備ができたら、イタチが出没しそうな場所に設置しましょう。
庭や外壁の周り、特に侵入されやすい箇所の近くがおすすめです。
「でも、どうやってイタチを追い払うの?」って思いますよね。
実は、ペットボトルの水が太陽光や街灯の光を反射して、キラキラと光るんです。
この不規則な光の動きが、イタチにとっては不気味で危険な感じがするみたい。
「ここは安全じゃないぞ」って警戒心を抱かせるんです。
効果を高めるコツは以下の3つ。
- 複数のペットボトルを使う
- 風で動きやすいように軽く設置する
- 定期的に水を入れ替える
でも、実際に多くの人がこの方法で効果を実感しているんです。
しかも、このペットボトル対策、コストはほぼゼロ。
エコで、お財布にも優しい。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるんです。
ただし、強風の日は飛ばされないように注意してくださいね。
「せっかく設置したのに、台風で飛んでっちゃった〜」なんてことにならないように。
この簡単DIY、今すぐ試してみませんか?
きっと、イタチ対策の新たな味方になってくれるはずです。
コーヒーかすを使った天然の忌避剤の作り方
コーヒー好きの方、朝のコーヒーかすを捨てる前にちょっと待ってください!実は、このかすがイタチ対策の強い味方になるんです。
「えっ、コーヒーかすでイタチが寄ってこなくなるの?」そう思った方も多いはず。
でも、本当なんです。
コーヒーの強い香りが、イタチの敏感な鼻を刺激して、寄ってこなくなるんです。
さて、コーヒーかすを使った天然の忌避剤の作り方、早速見ていきましょう。
- 使用済みのコーヒーかすを集める
- 天日で完全に乾燥させる
- 乾燥したかすを小さな布袋や網袋に入れる
- イタチの侵入が心配な場所に設置する
湿ったままだとカビの原因になっちゃうんです。
「わー、イタチ対策のつもりが家中カビだらけに...」なんて悲惨な結果は避けたいですよね。
効果を高めるコツはいくつかあります。
- 定期的に新しいかすに交換する(1週間に1回程度)
- 複数箇所に設置する
- 他の香りの強いハーブ(ミントやラベンダーなど)と組み合わせる
確かに室内で使うには匂いが気になるかもしれません。
だから、外壁の周りや庭など、屋外での使用がおすすめです。
この方法、コストはほぼゼロ。
しかも、コーヒーかすの再利用なので環境にも優しい。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるんです。
ただし、雨の日は効果が薄れるので、屋根のある場所に設置するのがコツ。
「せっかく置いたのに、雨で流されちゃった〜」なんてことにならないように気をつけてくださいね。
毎日のコーヒータイムが、イタチ対策にもなる。
なんだかワクワクしませんか?
さあ、明日の朝からさっそく始めてみましょう!
ハッカ油スプレーで侵入経路をブロック!作り方と使用法
ハッカ油って知ってますか?あのスーっとする爽やかな香り。
実は、これがイタチ撃退の強力な武器になるんです。
「えっ、そんな香りでイタチが逃げるの?」って思いますよね。
でも、イタチの鼻はとっても敏感。
人間には爽やかな香りでも、イタチにとっては強烈な刺激になるんです。
さて、ハッカ油スプレーの作り方と使い方、詳しく見ていきましょう。
まずは作り方です。
- スプレーボトルを用意する
- 水200mlに対してハッカ油を10滴ほど入れる
- よく振って混ぜる
簡単でしょ?
次に使い方です。
- イタチの侵入が心配な場所に直接スプレーする
- 特に、壁の隙間や換気口の周りなどを重点的に
- 2?3日おきに再度スプレーして効果を持続させる
「一回やったからもう大丈夫」なんて油断は禁物です。
イタチは賢い動物なので、継続的な対策が必要なんです。
「でも、ハッカ油って強すぎない?」って心配な方もいるでしょう。
確かに原液は刺激が強いので、必ず水で薄めて使ってくださいね。
上記の割合なら、人間にも優しく、イタチにも効果的です。
この方法、メリットがたくさんあるんです。
- 材料が簡単に手に入る
- 自然由来なので環境に優しい
- 爽やかな香りで家中スッキリ
「イタチは追い払えたけど、大切なカーテンが変色しちゃった〜」なんて悲劇は避けたいですよね。
ハッカ油スプレー、イタチ対策と同時に、お部屋の消臭にも一役買ってくれます。
一石二鳥の効果、試してみる価値ありですよ!
アルミホイルの音と光でイタチを驚かせる設置方法
キッチンでおなじみのアルミホイル、実はイタチ対策の強力な味方になるんです。その秘密は、音と光にあります。
「えっ、アルミホイルでイタチが逃げるの?」って思いますよね。
でも、イタチの繊細な感覚を利用すれば、こんな身近なものでも十分な効果があるんです。
では、アルミホイルを使ったイタチ対策の方法を詳しく見ていきましょう。
まず、準備するものは以下の通り。
- アルミホイル
- はさみ
- 紐やテープ(設置用)
- アルミホイルを20cm四方くらいに切る
- 端を少し折り曲げて、風で飛ばされにくくする
- イタチの侵入が心配な場所に、紐やテープで固定する
- 複数枚を間隔を空けて設置する
これが重要なんです。
なぜかって?
それには2つの理由があります。
1つ目は音。
風で揺れるアルミホイルが「カサカサ」という音を立てます。
この不規則な音が、イタチを警戒させるんです。
「何か危険なものがいるぞ」って感じさせるわけです。
2つ目は光。
アルミホイルが太陽光や街灯の光を反射して、キラキラと光ります。
この予測不能な光の動きが、イタチにとっては不気味で危険な感じがするみたい。
「でも、そんな簡単なことでイタチが寄ってこなくなるの?」って半信半疑かもしれません。
でも、実際に多くの人がこの方法で効果を実感しているんです。
この方法、メリットがたくさん。
- 材料が安くて手に入りやすい
- 設置が簡単
- 環境に優しい
「せっかく設置したのに、台風で全部飛んでっちゃった〜」なんてことにならないように。
アルミホイル、キッチンだけじゃもったいない。
イタチ対策の新たな主役として、さっそく活躍させてみませんか?
ソーラーライトで夜間の侵入を防ぐ!効果的な配置のコツ
夜になるとイタチの活動が活発になるって知っていましたか?だからこそ、夜間の対策が重要なんです。
そこで登場するのが、ソーラーライト。
このエコな照明器具が、イタチ対策の強力な味方になるんです。
「えっ、ただの明かりでイタチが寄ってこなくなるの?」って思いますよね。
でも、イタチは用心深い動物。
突然の明かりに警戒心を抱くんです。
では、ソーラーライトを使ったイタチ対策の方法を詳しく見ていきましょう。
まず、準備するものは以下の通り。
- 動きを感知するソーラーライト(2?3個以上)
- 設置用の杭やフック
- イタチの侵入経路を予想する(庭、フェンス周り、外壁など)
- その経路上に、2?3メートル間隔でソーラーライトを設置
- 可能であれば、異なる高さに配置(地面、腰高、頭上など)
- 動体センサーの感度を調整(小動物でも反応するように)
これが重要なんです。
なぜかって?
それには2つの理由があります。
1つ目は、死角をなくすため。
1つだけだと、イタチが光を避けて通る可能性があります。
複数あれば、逃げ場をなくせるんです。
2つ目は、驚かせる効果を高めるため。
あちこちで不規則に光が点くことで、イタチの警戒心を強めることができます。
「でも、ご近所迷惑にならない?」って心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
最近のソーラーライトは、程よい明るさで設計されています。
それに、動体センサー付きなら必要なときだけ点灯するので、ムダな光害も防げます。
この方法、メリットがたくさん。
- 電気代がかからない
- 設置が簡単
- 防犯効果も期待できる
- 庭の雰囲気づくりにも一役買う
「せっかく設置したのに、肝心なときに光らない〜」なんてことにならないように、時々チェックしてくださいね。
ソーラーライトを使ったイタチ対策、環境にも優しくて一石二鳥。
夜の庭が明るくなるだけでなく、イタチも寄ってこなくなる。
そんな素敵な効果を期待して、さっそく始めてみませんか?
きっと、夜の庭の雰囲気も変わって、新たな楽しみが見つかるかもしれません。
イタチ対策が、思わぬところで生活を豊かにする。
そんな発見があるかもしれないんです。
ソーラーライトの選び方から設置方法まで、ちょっとしたコツを押さえれば、誰でも簡単に始められます。
イタチ対策と同時に、エコな生活への第一歩。
一度試してみる価値は十分にありそうですね。