イタチによる果樹被害の特徴と予防策は?【低い枝の果実が危険】果樹園を守る、季節別対策テクニック5つ

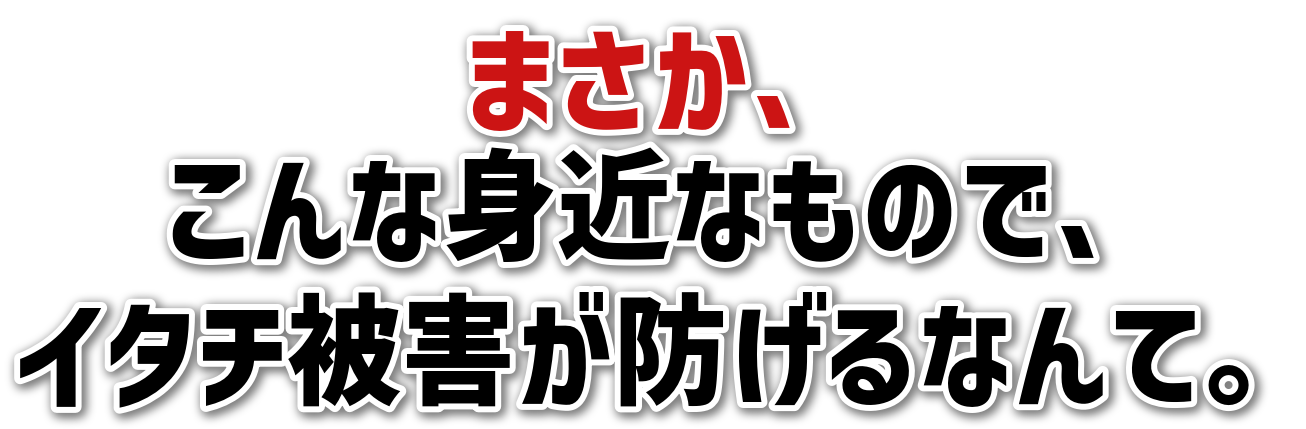
【この記事に書かれてあること】
果樹園や家庭菜園でイタチの被害に悩んでいませんか?- イタチは低い枝の果実を好んで狙う習性がある
- 完熟直前の甘い果実がイタチの標的になりやすい
- 高さ2メートル以上のフェンスが効果的な防護策
- ネットや誘引で低い枝の果実を保護する
- 草刈りなどの環境整備でイタチを寄せ付けない
- ペットボトルやCDを使った意外な撃退法も有効
- 収穫時期の管理と被害跡の適切な処理で再発を防ぐ
実は、イタチは低い枝の果実を好んで狙うんです。
でも、大丈夫。
効果的な対策法があります。
この記事では、イタチによる果樹被害の特徴と、収穫量を90%も増やせる秘訣をご紹介します。
高さ2メートル以上のフェンス設置や、ペットボトルを使った意外な撃退法など、すぐに実践できる方法が満載。
「今年こそはイタチに負けない!」そんな気持ちで、一緒に対策を学んでいきましょう。
【もくじ】
イタチによる果樹被害の特徴と影響

イタチが狙う果実の特徴「低い枝に要注意!」
イタチは低い枝の果実を好んで狙います。これは、イタチの身体的特徴と行動パターンに深く関係しているんです。
イタチは体長20〜40センチメートルほどの小型の動物です。
そのため、地面から手の届く高さの果実が狙いやすいターゲットになっちゃうんです。
「えっ、そんな低いところばかり?」と思うかもしれません。
でも、イタチの特徴をよく知ると、なるほどと納得できるはずです。
- 身軽で敏捷な動き:低い枝なら素早く接近できる
- 小さな体:高い場所より低い場所の方が安定して果実にアクセスできる
- 夜行性:暗闇でも地面に近い果実なら見つけやすい
でも、それは大きな間違い。
むしろ「低いところこそが危険」なんです。
「じゃあ、低い枝の果実はどうすればいいの?」そう思った方、安心してください。
対策はちゃんとあるんです。
例えば、低い枝にネットを巻いたり、枝を高く誘引したりする方法があります。
これらの対策を施せば、イタチの被害をぐっと減らすことができるんです。
低い枝に注目することが、果樹を守る第一歩。
それが、イタチ対策の秘訣なんです。
果実の熟度とイタチ被害の関係「完熟前がねらい目」
イタチは完熟直前の甘い果実を特に好んで狙います。これは、果実の熟度とイタチの嗅覚が密接に関係しているからなんです。
完熟前の果実は、甘い香りを強く放ちます。
この香りが、イタチの鋭い嗅覚を刺激するんです。
「えっ、イタチってそんなに嗅覚がいいの?」と驚く方もいるでしょう。
実は、イタチの嗅覚は人間の40倍以上も優れているんです。
- 完熟前の果実:糖度が上がり、甘い香りが強くなる
- イタチの嗅覚:人間の40倍以上の感度
- 夜間の活動:香りを頼りに果実を探す
「美味しそうな香りがするぞ」とばかりに、果樹園に集まってくるんです。
対策としては、収穫のタイミングを少し早めるのが効果的です。
完熟する前に収穫すれば、イタチを寄せ付けにくくなります。
「でも、早く収穫したら味が落ちるんじゃ...」そう心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
収穫後の適切な保管方法を工夫すれば、十分な味を保つことができるんです。
例えば、リンゴなら収穫後に冷暗所で保管すると、甘みが増していきます。
ブドウなら、房ごとに新聞紙で包んで保管すると、徐々に糖度が上がっていくんです。
完熟前の収穫と適切な保管。
これが、イタチから果実を守りつつ、美味しさも確保する秘訣なんです。
被害を受けやすい果樹の種類「甘い果実に集中」
イタチが特に好んで食べる果実は、甘みの強い種類です。リンゴ、ブドウ、イチゴ、スモモなどが、イタチの主なターゲットになっちゃうんです。
これらの果実に共通するのは、糖度の高さ。
イタチは甘いものが大好きで、高カロリーの食べ物を本能的に求めるんです。
「えっ、イタチってそんなに甘いもの好きなの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、野生動物の多くは効率よくエネルギーを摂取するため、甘い食べ物を好む傾向があるんです。
- リンゴ:果肉が柔らかく、糖度が高い
- ブドウ:小さな実が房になっていて、食べやすい
- イチゴ:香りが強く、イタチを引き寄せやすい
- スモモ:熟すと甘みが増し、イタチの好物に
「じゃあ、甘い果実は諦めるしかないの?」そんなことはありません。
対策をしっかり行えば、甘い果実も守ることができるんです。
例えば、ネットや金網で果実を覆ったり、イタチの嫌いな匂いのする植物(ラベンダーやミントなど)を近くに植えたりするのが効果的です。
また、果樹園の周りにフェンスを設置するのも有効な方法です。
甘い果実を守るコツは、イタチの特性をよく理解し、適切な対策を講じること。
それが、美味しい果実を守り抜く秘訣なんです。
イタチの果樹被害は昼と夜「どちらが深刻?」
イタチの果樹被害は、夜間の方がはるかに深刻です。これは、イタチの生態と深く関係しているんです。
イタチは典型的な夜行性動物。
日中はほとんど活動せず、日が沈むと活発に動き出します。
「えっ、じゃあ昼間は安全なの?」と思う方もいるでしょう。
実は、そう単純ではないんです。
- 夜間:イタチの活動のピーク時間
- 暗闇:イタチの目は暗闇でも良く見える
- 静寂:人間の活動が少なく、安心して行動できる
暗闇の中、静かに果樹に忍び寄り、甘い果実を食べ放題。
人間の目を気にせず、ゆっくりと食事を楽しめるんです。
一方、昼間の被害は比較的少ないものの、まったくないわけではありません。
特に、人の気配が少ない静かな果樹園では、昼間でもイタチが現れることがあるんです。
対策としては、夜間の防御を重点的に行うことが大切です。
例えば、夕方に果実を収穫する、夜間にライトを点灯する、動きセンサー付きの音や光の装置を設置するなどが効果的です。
「でも、毎晩見回るのは大変...」そう思う方も多いでしょう。
その場合は、自動化された防御システムを導入するのも一案です。
夜間重点の対策を行いつつ、昼間も油断しない。
これが、イタチの被害から果樹を守る秘訣なんです。
イタチの被害放置は危険!「収穫量激減の恐れ」
イタチの被害を放置すると、果樹園の収穫量が激減する恐れがあります。これは、イタチの繁殖力と食欲が驚くほど旺盛だからなんです。
一度イタチが果樹園を「美味しい食事処」と認識すると、どんどん仲間を呼んできてしまいます。
「えっ、そんなに増えるの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、イタチは年に2回繁殖期があり、一度に3〜8匹の子供を産むんです。
- 繁殖力:年2回の繁殖期、一度に3〜8匹出産
- 食欲旺盛:体重の10〜15%を毎日摂取
- 学習能力:一度餌場を覚えると、繰り返し訪れる
果実がどんどん食べられ、収穫量が年々減少。
最終的には果樹園全体が荒廃し、経営が立ち行かなくなる...。
「そんな...」と思わず声が出てしまいますね。
でも、大丈夫です。
早めの対策を講じれば、こんな未来は避けられるんです。
例えば、フェンスの設置、ネットの利用、忌避剤の使用などが効果的です。
また、定期的な見回りや、被害跡の素早い処理も重要です。
「でも、対策にはお金がかかるんじゃ...」そう心配する方もいるでしょう。
確かに初期投資は必要ですが、長期的に見れば収穫量の維持につながり、結果的に経済的なメリットが大きいんです。
被害の早期発見と迅速な対応。
これが、果樹園を守り、豊かな収穫を続ける秘訣なんです。
効果的な果樹園の防護策

高さ2メートル以上のフェンス設置「侵入を阻止」
イタチの侵入を防ぐなら、高さ2メートル以上のフェンスが効果的です。これで果樹園をがっちりガードできちゃいます。
「えっ、2メートルもいるの?」って思った方もいるかもしれませんね。
でも、イタチってすごくジャンプ力があるんです。
なんと、垂直に1メートル以上跳べちゃうんです。
だから、2メートル以上のフェンスが必要なんですね。
フェンスを設置する時は、こんなポイントに気をつけましょう。
- 地面にしっかり埋め込む(イタチは穴を掘って侵入することも)
- 金網タイプを選ぶ(イタチが登りにくい)
- 網目は2センチ以下(小さなイタチも通れない)
確かに初期投資は必要ですが、長い目で見ると絶対にお得です。
イタチの被害で毎年失う果実を考えると、むしろ節約になるんです。
例えば、100平方メートルの果樹園なら、フェンスの設置費用は約10万円くらい。
でも、イタチの被害で年間10万円以上の損失が出ている農家さんも多いんです。
そう考えると、1年で元が取れちゃうかも。
フェンスを設置したら、定期的に点検するのも忘れずに。
「ここに穴が空いてる!」なんてことがないように、こまめにチェックしましょう。
ガッチリ守って、美味しい果実をたくさん収穫しましょう!
低い枝の果実保護法「ネットと誘引で対策」
低い枝の果実を守るなら、ネットで包むか、枝を高く誘引するのが効果的です。これで、イタチの大好物である低い位置の果実を守れちゃいます。
「でも、どうやって守ればいいの?」って思いますよね。
具体的な方法をご紹介しましょう。
- ネットで包む方法
- 細かい網目のネットを選ぶ(1センチ四方くらいがおすすめ)
- 果実だけでなく、枝全体を包み込む
- ネットの端はしっかり固定(イタチは賢いので、隙間を見つけちゃいます)
- 枝を高く誘引する方法
- 支柱を立てて、枝を上に向けて誘導
- 果実が地面から1.5メートル以上の高さになるように
- 誘引する時は枝を傷つけないよう注意
でも、一度慣れてしまえば、さっさとできるようになりますよ。
誘引も、コツさえつかめば簡単です。
例えば、リンゴの木なら、主枝を斜めに誘引して、その上に果実をつける側枝を配置する「開心形」という仕立て方があります。
これなら、自然と果実が高い位置につくんです。
大切なのは、イタチの目線で考えること。
「もし自分がイタチだったら、どこから攻めるだろう?」なんて想像してみるのも面白いかも。
そうすれば、効果的な対策が見えてくるはずです。
低い枝の果実をしっかり守って、イタチに「ちぇっ、手が届かないよ〜」って言わせちゃいましょう!
イタチを寄せ付けない環境作り「草刈りが重要」
イタチを寄せ付けない環境作りには、なんと言っても草刈りが重要です。きれいに刈り込まれた果樹園は、イタチにとっては居心地が悪いんです。
「え?草を刈るだけでイタチが来なくなるの?」って思うかもしれませんね。
実は、イタチは身を隠せる場所を好むんです。
草むらは、まさにイタチにとっての楽園。
そこで、草刈りをしっかりやることで、イタチの隠れ家をなくしちゃうんです。
具体的には、こんな風に草刈りをしましょう。
- 果樹園の周囲5メートルは特に丁寧に刈る
- 草の高さは5センチ以下に保つ
- 月に1回は必ず刈る(成長が早い時期は2週間に1回)
- 刈った草はすぐに片付ける(放置するとイタチの隠れ家に)
でも、定期的にやれば、そんなに大変じゃないんです。
むしろ、果樹の管理がしやすくなって一石二鳥。
例えば、草刈り機を使えば、広い面積もあっという間。
休日の朝、さわやかな空気の中で草刈りをするのは、意外と気持ちいいものですよ。
「シャキシャキ」って音を聞きながら、「よし、これでイタチは来ないぞ!」って思うと、なんだかワクワクしてきます。
草刈り以外にも、果樹園をきれいに保つことが大切です。
落ち葉や枯れ枝は速やかに片付けましょう。
イタチにとって、これらも格好の隠れ家になっちゃうんです。
きれいな果樹園は、イタチにとっては「ここは危険だぞ」というサイン。
人間にとっては「ここは大切に管理されている」という証。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるんです。
さあ、草刈り機を持って、イタチ撃退大作戦、始めましょう!
イタチvs鳥類「果樹被害の比較と対策の違い」
イタチと鳥類、どっちの被害が深刻か知っていますか?実は、イタチの方が厄介なんです。
鳥と比べると、イタチの被害は局所的ですが、一度侵入すると継続的に被害が出やすいんです。
「えっ、鳥の方が多そうなのに?」って思いませんか?
確かに、鳥の被害は広範囲に及びます。
でも、イタチは一度お気に入りの場所を見つけると、そこに住み着いちゃうんです。
つまり、毎日のように被害が出るってわけ。
では、イタチと鳥の被害の特徴を比べてみましょう。
- イタチの被害
- 低い位置の果実を狙う
- 一度に大量の果実を食べる
- 夜間に活動するため、対策が難しい
- 鳥の被害
- 高い位置の果実も狙う
- つつかれた跡が残る程度のことも
- 昼間に活動するため、対策が立てやすい
イタチ対策はフェンスや低い枝の保護が中心。
一方、鳥対策は防鳥ネットや音による追い払いが主流です。
例えば、ブドウ園の場合。
鳥対策なら、ブドウの房を紙袋で包むだけでOK。
でも、イタチ対策なら、棚全体をネットで覆う必要があるんです。
「う〜ん、大変そう...」って思いますよね。
でも、被害を考えると、やる価値は十分あります。
面白いのは、イタチ対策が鳥対策にもなること。
高いフェンスは鳥も侵入しにくいんです。
逆に、鳥対策だけじゃイタチは防げません。
「一石二鳥」どころか「一石二獣」ならぬ「一石二鳥獣」ってところでしょうか。
結局のところ、イタチと鳥、両方の対策をバランスよく行うのが賢明。
「よし、これで完璧!」って思えるまで、少しずつ対策を重ねていきましょう。
果樹園が動物たちにとって「立ち入り禁止エリア」になれば、美味しい果実がたくさん収穫できるはずです!
イタチ対策における季節別アプローチ「春秋に注意」
イタチ対策、実は季節によって変えるのがコツなんです。特に気をつけたいのが春と秋。
この時期はイタチが特に活発になるんです。
「え?なんで春と秋なの?」って思いますよね。
実は、イタチの繁殖期が春と秋なんです。
子育てのために餌を求めて、果樹園に侵入してくる確率が高くなるんです。
では、季節別のイタチ対策をご紹介しましょう。
- 春(3月〜5月)
- 巣作りの材料になりそうなものを片付ける
- 果樹の新芽をイタチから守る
- フェンスの点検と補修を行う
- 夏(6月〜8月)
- 果実の成長を見守りながら、低い枝の保護を始める
- 草刈りを頻繁に行い、隠れ場所をなくす
- 秋(9月〜11月)
- 収穫期に入るので、果実の保護を強化
- 落ち葉の清掃を小まめに行う
- 夜間の見回りを増やす
- 冬(12月〜2月)
- 剪定した枝の片付けを徹底
- イタチの足跡や糞を見つけたら、すぐに対策
でも、コツコツやれば、そんなに大変じゃないんです。
例えば、春の巣作り対策。
庭の掃除をする時に、ついでに巣材になりそうな枯れ草や小枝を片付けるだけ。
「よし、これでイタチさんお断り!」って気分で掃除すれば、楽しくできちゃいます。
秋の収穫期の対策も大切。
「今年こそは全部自分で食べるぞ!」って意気込んで、果実をしっかり守りましょう。
夜な夜な現れるイタチさんとの知恵比べ、勝つのは果たしてどっち?
季節に合わせた対策で、一年中イタチを寄せ付けない果樹園作り。
「うちの果樹園は、イタチお断りです!」って胸を張って言えるようになりましょう。
そうすれば、美味しい果実がたくさん収穫できるはずです。
がんばって対策、始めましょう!
イタチ対策の驚くべき裏技と管理方法

ペットボトルの反射光でイタチを撃退!「設置方法」
ペットボトルの反射光を使えば、イタチを簡単に撃退できちゃいます。これって、まるで魔法みたいでしょ?
「えっ、ペットボトルだけでイタチが追い払えるの?」って思うかもしれませんね。
でも、本当なんです。
イタチは光に敏感な動物なんです。
突然の光の反射に驚いて、逃げ出しちゃうんです。
では、具体的な設置方法を見てみましょう。
- 透明なペットボトルを用意する(2リットルサイズがおすすめ)
- ボトルの中に水を半分くらいまで入れる
- 果樹の周りに3〜5メートル間隔で設置する
- ボトルが動くように、紐で枝にゆるく結ぶ
でも、実はこれがすごく効果的なんです。
風で揺れるペットボトルが、月明かりや街灯の光を反射して、キラキラと光るんです。
これがイタチにとっては「ピカッ」という不気味な光になるわけです。
例えば、10本の果樹がある小さな果樹園なら、20本くらいのペットボトルを設置するといいでしょう。
「わぁ、まるでイルミネーションみたい!」なんて、楽しい気分にもなれちゃいますよ。
ただし、注意点もあります。
定期的にボトルの水を交換しましょう。
夏場は特に、ボトルの中で藻が発生しやすいんです。
「えっ、面倒くさそう...」なんて思わないでください。
水を交換するついでに、ボトルの位置を少し変えるのもおすすめです。
イタチが慣れっこにならないようにするためです。
この方法、エコで経済的で効果的。
まさに一石三鳥のイタチ対策なんです。
さあ、今すぐペットボトルを探してみましょう!
CDの動く反射でイタチを威嚇「簡単な吊るし方」
古いCDを使って、イタチを威嚇する方法があるんです。これ、すごく効果的なんですよ。
「えっ、CDってあの音楽を聴くやつ?」って思った人もいるかもしれませんね。
そうなんです。
あの平たい円盤が、イタチ撃退の強い味方になってくれるんです。
CDの表面はピカピカ光りますよね。
この反射光が、イタチにとってはとっても怖いものなんです。
風で揺れるCDの光の動きが、イタチの目をくらませちゃうんです。
では、CDの簡単な吊るし方を見てみましょう。
- 使わなくなったCDを集める(10枚くらいあると◎)
- CDの真ん中の穴に、長さ30センチくらいの丈夫な糸を通す
- 糸の両端を結んで輪っかを作る
- 果樹の枝にCDを吊るす(地面から1〜1.5メートルの高さがベスト)
- CDが自由に回転できるよう、ゆるめに結ぶ
でも、これが本当に効果があるんです。
風が吹くたびにクルクル回るCDが、キラキラ光を反射します。
まるでディスコボールみたいです。
例えば、リンゴの木なら1本に2〜3枚のCDを吊るすといいでしょう。
「わぁ、果樹園がキラキラしてきれい!」なんて楽しくなっちゃいますよ。
ただし、注意点もあります。
CDの表面が汚れたら、柔らかい布で優しく拭いてあげましょう。
「えっ、お手入れが必要なの?」って思うかもしれません。
でも大丈夫、たまに拭くだけでOKです。
きれいなCDの方が、より強い反射光を出せるんです。
この方法、お金はほとんどかからないのに、効果は抜群。
しかも、古いCDの再利用にもなるんです。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるかも?
さあ、今すぐ使っていないCDを探してみましょう!
辛味スプレーでイタチを寄せ付けない「作り方と使用法」
辛味スプレーを使えば、イタチを寄せ付けないんです。これ、すごく効果的な方法なんですよ。
「えっ、辛いものがイタチに効くの?」って思いますよね。
実は、イタチは辛い匂いが大嫌いなんです。
この特性を利用して、イタチを遠ざけちゃおう、というわけです。
では、辛味スプレーの作り方と使用法を見てみましょう。
- 材料を用意する
- 唐辛子(一味唐辛子でもOK)大さじ2
- にんにく 2かけ
- 水 500ml
- スプレーボトル 1本
- 作り方
- 唐辛子とすりおろしたにんにくを水に入れる
- よく混ぜて一晩置く
- ざるでこして、スプレーボトルに入れる
- 使用方法
- 果樹の周りの地面や低い枝にスプレーする
- 3日に1回くらいのペースで繰り返す
- 雨が降った後は必ず再度スプレーする
家にある材料で、すぐに作れちゃうんです。
例えば、ブドウ畑なら、株の周りの地面にぐるっとスプレーしてあげるといいでしょう。
「うわっ、辛そう!」って感じる匂いが、イタチを寄せ付けないんです。
ただし、注意点もあります。
果実に直接スプレーしないでください。
「えっ、辛いブドウになっちゃうの?」なんて心配しなくていいですよ。
地面や葉っぱにスプレーするだけでOKです。
この方法、材料費はほとんどかからないのに、効果は抜群。
しかも、化学物質を使わない自然な方法なんです。
環境にも優しいし、お財布にも優しい。
まさに一石二鳥のイタチ対策です。
さあ、今すぐキッチンに行って、材料を探してみましょう。
辛味スプレーで、イタチに「ここは辛いところだから近寄るな」ってメッセージを送っちゃいましょう!
収穫時期の管理で被害激減!「タイミングが重要」
収穫時期をうまく管理すれば、イタチの被害を大幅に減らせるんです。これ、すごく重要なポイントなんですよ。
「えっ、収穫の時期を変えるだけで被害が減るの?」って思いますよね。
実は、イタチは完熟した果実が大好物なんです。
だから、収穫のタイミングを少し早めることで、被害を激減させることができるんです。
では、具体的な管理方法を見てみましょう。
- 果実の状態をよく観察する
- 色づきが8割くらいになったら収穫の準備
- 香りが強くなってきたら要注意
- 収穫のタイミング
- 完熟の2〜3日前を目安に収穫
- 朝または夕方の涼しい時間帯に行う
- 収穫後の管理
- 涼しい場所で保管し、追熟させる
- 定期的に状態をチェックする
大丈夫です。
果実には「追熟」という素晴らしい能力があるんです。
収穫後も熟成が進むんです。
例えば、モモなら、皮の色が緑から黄色に変わり始めたら収穫時期。
リンゴなら、赤みが8割くらいついたら収穫のサイン。
「へぇ、こんな風に見分けるんだ!」って新しい発見があるかもしれませんね。
ただし、注意点もあります。
果実の種類によって最適な収穫時期が違います。
「うわっ、難しそう...」って思わないでください。
観察を重ねれば、コツがつかめてきますよ。
この方法のすごいところは、イタチ対策になるだけでなく、果実の品質管理にもなること。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるかも?
さあ、今すぐ果樹園に行って、果実の様子を確認してみましょう。
「今日こそは、イタチより先に収穫するぞ!」って意気込んで、収穫の準備を始めましょう。
タイミングを制する者が、イタチ対策を制するんです!
被害跡の適切な処理「再発防止のカギ」
被害跡をしっかり処理することが、イタチ被害の再発を防ぐ重要なカギなんです。これ、見逃しちゃいけない大切なポイントですよ。
「えっ、被害を受けた後にも対策が必要なの?」って思いますよね。
実は、被害跡を放置すると、イタチがまた戻ってくる可能性が高くなっちゃうんです。
だから、適切な処理が大切なんです。
では、具体的な処理方法を見てみましょう。
- 被害果実の処理
- かじられた果実はすぐに取り除く
- ビニール袋に入れて密閉し、廃棄する
- 被害を受けた枝の手入れ
- かじられた部分を清潔なはさみで切除
- 切り口に園芸用殺菌剤を塗る
- 周辺の清掃
- 落ちた果実や葉っぱを綺麗に取り除く
- イタチの糞や足跡があれば消毒する
- 再発防止策
- 被害のあった場所に忌避剤をまく
- 近くの木にもペットボトルやCDを設置
でも、これらの作業は、イタチに「ここはもう安全な餌場じゃないよ」というメッセージを送るために必要なんです。
例えば、リンゴの木がイタチに襲われたら、その日のうちに被害果実を取り除き、かじられた枝を切除。
周りの落ち葉もキレイに掃除。
「よし、これでイタチさんお断りだ!」って感じで徹底的に処理しちゃいましょう。
ただし、注意点もあります。
被害跡の処理は、手袋をして行ってください。
「えっ、素手じゃダメなの?」って思うかもしれません。
イタチの糞には病気の原因になる菌がいることがあるんです。
安全第一で作業しましょうね。
この方法、手間はかかりますが、効果は抜群。
しかも、果樹の健康管理にもなるんです。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるかも?
さあ、イタチ被害を見つけたら、すぐに行動を起こしましょう。
「この木は私が守る!」って気持ちで、しっかり処理していきましょう。
適切な処理が、美味しい果実を守る第一歩なんです。
再発防止の秘訣は、迅速で丁寧な処理にあるんです。
イタチに隙を与えず、果樹園を守り抜きましょう!